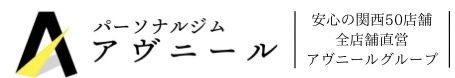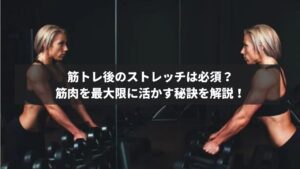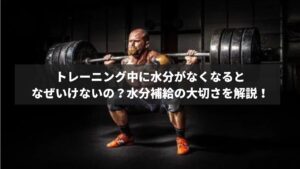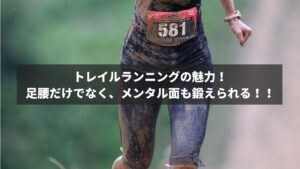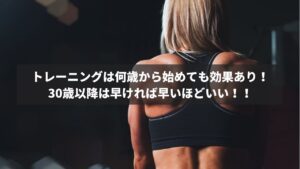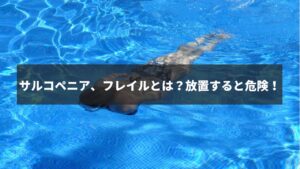関節可動域とは、関節が動かせる角度の範囲を示すことであり、運動機能や身体の健康状態を評価するうえで重要な指標です。
人の体は約200以上の関節から構成され、それぞれが異なる方向や角度に動くことが可能です。
例えば、肘関節は主に屈曲と伸展の動きに限られますが、肩関節は前後・左右・ひねるといった多方向の運動が可能で、可動域の広さが大きな特徴の関節です。
このように関節ごとに本来備わっている「正常可動域」があり、日本整形外科学会などが標準値を定めています。
関節可動域は、年齢、性別、体格、筋肉や靭帯の柔軟性、さらには日常生活の習慣によって大きく影響を受けます。
加齢とともに筋肉や腱が硬くなり、また関節の潤滑を担う関節液の分泌も減少するため、可動域は徐々に狭くなります。
運動不足も可動域制限の大きな要因の一つであり、長時間同じ姿勢で過ごす習慣や身体を動かさない生活は、関節周囲の組織を硬化させ、動きの制限を招いてしまいます。
さらに、関節炎や骨折後の拘縮、変形性関節症といった疾患は可動域を著しく低下させることがあります。
可動域が制限されると、姿勢の悪化や歩行動作の障害、肩こりや腰痛といった慢性的な不調が起きやすくなります。
例えば、股関節の可動域が狭いと正しい歩幅で歩けなくなり、代償的に腰や膝へ負担がかかります。
また、肩関節の動きが悪いと衣服の着脱や物を高い場所に持ち上げる動作が困難になるなど、日常生活の質の低下してしまいます。
そのため、関節可動域は「生活のしやすさ」や「健康寿命」に直結する要素であるといえます。
維持・改善のためには、ストレッチや運動が欠かせません。
静的ストレッチは筋肉や腱をじっくり伸ばし、柔軟性を高めるのに有効です。
さらに、関節を支える筋肉を鍛えることも大切で、柔軟性と筋力の両立によってはじめて関節は安定的かつ広い範囲で動かすことができます。
ウォーキングやヨガ、ピラティスといった全身運動は、関節を多方向に動かすため特に有効です。
加えて、デスクワーク中に1時間ごとに体を伸ばす、正しい姿勢を意識するなど、日常生活の小さな工夫も可動域の維持に寄与します。
以下は関節可動域を保つためのストレッチです。
ぜひ一度やってみてください。
股関節
・開脚ストレッチ
床に座って足を左右に大きく開き、体を前にゆっくり倒す。
→ 股関節の外転・屈曲を広げる効果。
・膝抱えストレッチ
仰向けで片膝を胸に抱える。左右交互に。
→ 股関節の屈曲可動域を保つ。
膝関節
・ハムストリングストレッチ(太もも裏)
椅子に浅く座り、片足を前に伸ばしてかかとを床につけ、体を前に倒す。
→ 膝伸展時の柔軟性を維持。
足首関節
・アキレス腱伸ばし
壁に手をつき、片足を後ろに引き、かかとを床に押しつける。
→ 足首の背屈可動域を保つ。
肩関節
・クロスアームストレッチ
片腕を胸の前に伸ばし、反対の腕で抱えて引き寄せる。
→ 肩関節の水平内転を広げる。
・バンザイストレッチ
両手を頭上に上げ、できるだけ背伸びする。
→ 肩関節の屈曲・外転を保つ。